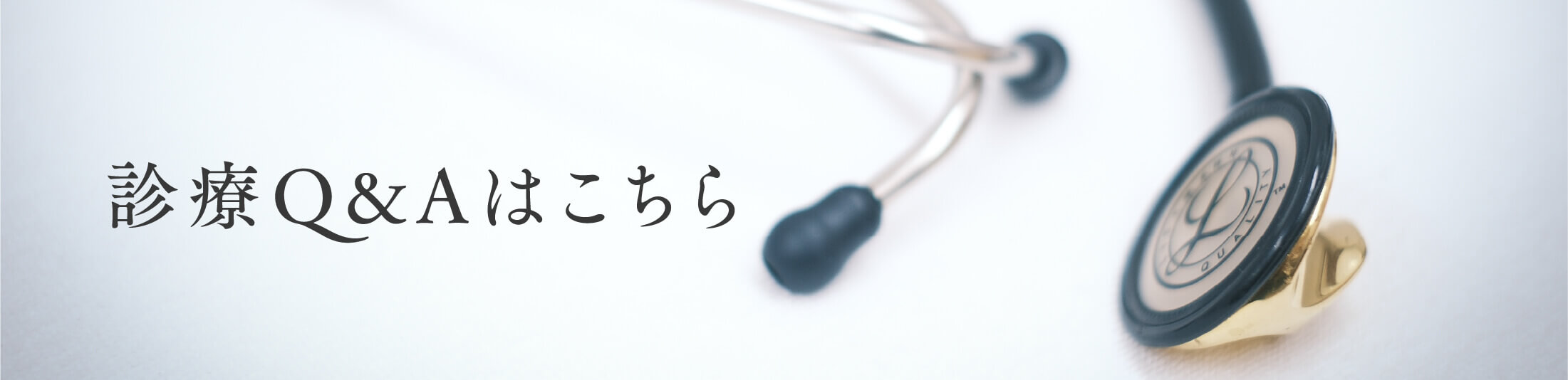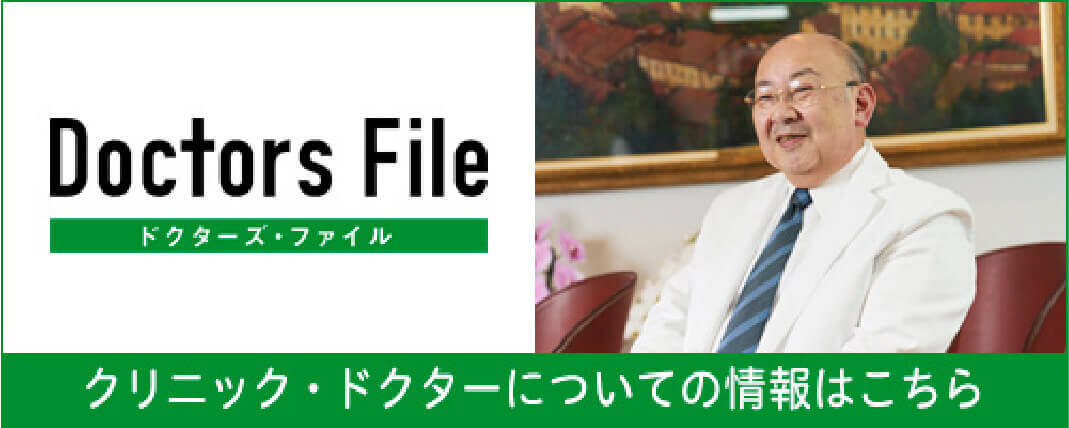地域に根ざした
質の高い専門医療を提供します。
質の高い専門医療を提供します。
NEWS
2024.03.17
脚で蹴る力はどれくらいか2

TREATMENT
診療について
-
時間 月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30〜12:00 ● ● ● ● ● ● - - 15:00〜18:00 ● ● ● - ● - - - 8:30〜12:00、15:00〜18:00木・土曜AMのみ 臨時休診あり
CATEGORY
臨床研究部

田辺医院では院長の症例治験、法医学分野での実績を活かし、地元医療に還元するための研究棟を設置しています。臨床試験に関する事項や、医学的な解明を必要とする法律上の案件に対して、公正な医学的判断を下す「法医学」の研究を行っています。
ACCESS
-
お車でお越しの方
北条バイパスから車で13分
駐車場あり/田辺医院前に2台完備、
松山市役所 北条支所前に14台完備
(普通自動車7台、軽四車7台) -
電車でお越しの方
JR予讃線「伊予北条駅」から「田辺医院」まで徒歩8分
-
バスでお越しの方
伊予鉄バス「北条本町」バス停から徒歩5分